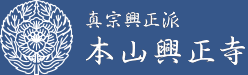【二百八十三】仏護寺十二坊 その五 興正寺の意見
2025.07.26
仏護寺十二坊のうちの三箇寺の住持が町の大年寄役の者の家屋に預け置かれ、十一箇寺が閉門となったため、仏護寺の本寺である興正寺は、元禄十四年(一七〇一)冬、使僧として正恩寺を広島に派遣しました。正恩寺は広島で寺社奉行、それに十二坊の住持たちと面談し、京都に戻りました。正恩寺は京都に戻ったあと、興正寺に広島の状況を報告するとともに、今後の対応の仕方を協議しました。そして、元禄十五年(一七〇二)春、正恩寺は、再び、広島へと向かいました。広島に着くと、正恩寺は広島藩の年寄衆、寺社奉行たちに会い、興正寺としての意見を伝えました。
こたひの一儀、奉行中より申わたされしを違背せしハ、十二坊不調法のいたりなり、さるゆゑ閉門申つけられし事とおほゆ、しかるに閉門永々になりてハ、十二坊中数万人の旦方とやかくと狐疑猶予し、自然ハ改宗なとの騒動おこりなん事もはかりかたく、さありては興門跡外実の災厄此時にせまれり、あハれ十二坊らか麁忽のふるまひ宥免あり、閉門赦罪なしあたへられなハ、いと忝からん、はた十二坊とも願ひ奉りし寺帖判形の事も、これまてにたかハす、いたし来りしことく申つけられなは、とりわき忝かるへし(『知新集』)
正恩寺が藩に伝えた興正寺の意見です。このたび、十二坊の住持たちが藩の命令に従わず、寺内宗旨判形帖に十二坊の住持の判を据えるよう強く主張したことは、住持たちに過失があるのはもちろんのことで、そのために閉門を申しつけたものと思いますが、それでも長く閉門が続くと、十二坊の数万人もの檀家の人びとも何かと疑いをいだくことになり、おのずと人びとは十二坊の寺から離れ、改宗するといった騒動にも発展しそうで、そのようなことになれば興正寺も大いに面目を失うことになるため、十二坊の住持たちの粗忽な振る舞いを許し、また、十二坊の願いの通り、寺内宗旨判形帖にはこれまでのまま十二坊の住持も判形を据えるということにしてもらえるならば、ありがたいことである、とあります。興正寺の意見は奉行に敬意を払いつつも、十二坊の住持たちをも助けるといった内容のものになっていました。
この意見のなか、十二坊中数万人の旦方とあって、十二坊の檀家の人びとの数を数万人と述べていますが、これは誇張して述べているのではありません。十二坊はそれぞれが、多くの末寺と檀家とをかかえた寺でした。江戸時代の後期のことですが、十二坊の一つである光福寺は二十七箇寺の末寺と、三十八箇寺の末寺の末寺、それに三千九百軒の檀家をかかえていました。同じく円竜寺は二十七箇寺の末寺と、二十一箇寺の末寺の末寺、それに四千六百軒の檀家をかかえていました。十二坊はそれぞれが格段に大きな寺であったのです。広島藩は十二坊を仏護寺の塔頭として捉えていますが、塔頭といわれるような寺ではなかったのです。
興正寺の意見は部分的に藩に受け入れられました。興正寺が意見を伝えたことで、町の大年寄役の者の家屋に預けられた十二坊のうちの三箇寺の住持は預け置きにされることを許され、のこりの十一箇寺の寺も閉門を許されたのです。
藩が十二坊に閉門を命じた時、十二坊の一つの蓮光寺は、ほかの十二坊があった寺町ではなく、別の場所に寺基を移していました。蓮光寺があったのは寺町から、幾分、離れた沼田郡の長束村です。そうならば、蓮光寺は立地の上では仏護寺の塔頭ではないということになります。それでも蓮光寺は塔頭だということで、寺内宗旨判形帖に判形を据えることができなくなり、ほかの十二坊と同様に閉門となりました。蓮光寺は寺基を移したあとも寺町のもとの境内地をそのまま所有していたので、寺町とは関わりがありましたが、それでもこれを理由に塔頭だというのは無理があります。しかし、この対応から、藩が十二坊というものをどのように考えていたのかを知ることができます。この時には蓮光寺のほか、正伝寺も寺町に寺基はありませんでした。正伝寺は最初から寺町に移転することもなく、ずっと別の場所にありました。正伝寺があったのは沼田郡の相田村です。ですが、この正伝寺も寺内宗旨判形帖に判形を据えることはできなくなり、閉門となっているのです。これらからするなら、十二坊の多くが仏護寺と同じ地に建っているということから、藩は、本来、十二坊は仏護寺とともにあるべきものであって、別の場所にあっても、それは仮に別の場所にあるだけだ、と考えていたことが分かります。
(熊野恒陽 記)