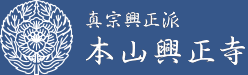【二百八十五】仏護寺十二坊 その七 藩と興正寺の考えの違い
2025.09.24
広島藩の寺社奉行から仏護寺に宛てられた口上書には、十二坊が仏護寺の境内に建っているということはこれまでいってきた通りだと書いてありました。広島藩は十二坊のことを塔頭といっていましたが、より大きな寺の境内に建っている寺というのであれば、まさしくそれは塔頭のことです。藩は十二坊の住持に寺内宗旨判形帖に判形を据えることを許しましたが、それは塔頭ではないから据えることを許したのではなく、塔頭ではあるが特別に許したのだといっているのです。
塔頭は禅宗で用いる語であり、真宗ではあまり用いられることはありませんが、塔頭寺院に相当する寺院は真宗にもあります。真宗ではこれを、寺中、地中、寺内、役僧、侍僧などといっていました。呼び方は地域によって異なります。これら寺中などといわれるものは、本坊にあたる大きな寺の境内地や近くの地にある小さな寺のことです。寺中は小規模ながら、門、本堂、庫裏を有し、それ自体が寺ではありますが、檀家はないか、もしくは少なく、住持が本坊にあたる大きな寺の法務を手伝うことで、成り立っていました。寺中は本坊に対しては従属的な立場で、檀家を増やし独立した寺となっていく寺中もありましたが、代々、本坊に従っているという寺中というものもありました。
真宗で塔頭というのであれば、それはこうした寺中のようなものを指すのが一般的です。これに対し、十二坊はそれぞれが多くの末寺と檀家をかかえた大きな寺です。しかも、十二坊はそれぞれ侍僧をもかかえていました。江戸時代の後半のことですが、十二坊の一つである報専坊には雷音、智英という二人の侍僧がおり、雷音は桁行六間半、梁行三間の建造物を有して、藩が認めた正式な寺号ではありませんが、西正寺と名乗っていました。智英も桁行五間半、梁行四間半の建造物を有し、正式なものではありませんが、教順寺と名乗っていました。十二坊が塔頭ならば、この西正寺などは塔頭の塔頭ということになります。そして、この侍僧に相当する者は仏護寺にもいました。仏護寺ではこれを役僧といっていましたが、仏護寺には三箇寺の役僧の寺がありました。品竜寺、浄満寺、実相寺の三箇寺です。この三箇寺は西本願寺の第十三世の良如上人の代に木仏の本尊の安置と寺号を名乗ることを許されています。つまりは正式な寺なのです。仏護寺の塔頭というのであれば、この三箇寺こそが塔頭に相当します。ところが、藩はこの三箇寺ではなく、十二坊の方を仏護寺の塔頭だとするのです。
十二坊の住持が寺内宗旨判形帖に判形を据えることができるようになったのは、興正寺が広島藩に判形を据えることができるようにしてもらいたいとの申し入れをしたからですが、その際、興正寺は使僧の正恩寺を介して、藩に十二坊は判形を据える権限を有する寺なのだということを主張していました。
十二坊、寺帖除かれ、仏護寺一判となる時ハ、仏護寺寺内僧、寺僧となりぬ、しかる時ハ真宗の寺法、寺僧に官職ゆるすことなし、十二坊ハ真宗にて本間の飛檐と申官職、七八十年前より許し来れる(『知新集』)
十二坊が寺内宗旨判形帖に判形を据えることなく、仏護寺だけが判形を据えるというのなら、十二坊は仏護寺の寺内僧、つまりは塔頭ということになる。しかし、西本願寺の寺法では、本坊に付属する塔頭の寺に官職、つまりは寺格を与えることはない。そうではあるが、十二坊は西本願寺から飛檐という寺格を与えられているし、それも七、八十年も前からその寺格のままである。興正寺はこう主張していました。興正寺は、十二坊は仏護寺の塔頭ではないのであるから、判形を据えることができるようにしてもらいたい、もし十二坊の住持が判形を据えることができず、仏護寺の住持だけが判形を据えるというのであれば、十二坊は仏護寺の塔頭ということになるではないかと述べているのです。判形を据えるか、据えないかということよりも、十二坊は塔頭か、塔頭ではないのかということを問題にしているのです。興正寺の主張しているのは、十二坊は塔頭ではないということです。これに対して、藩は十二坊に判形を据えることを認めましたが、一方で、十二坊は仏護寺の境内にある塔頭だといっていました。藩は、塔頭か、塔頭ではないのかということではなく、判形を据えさせるか、据えさせないかということだけを問題としているのです。藩は判形さえ据えさせておけば、興正寺、そして、十二坊の住持たちも、それで満足するのだと思っていたのでした。
(熊野恒陽 記)