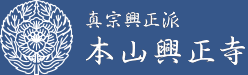【二百八十六】仏護寺十二坊 その八 仏護寺も十二坊を塔頭だと主張する
2025.10.25
広島藩は、元禄十五年(一七〇二)八月、興正寺の要望を受け入れ、仏護寺十二坊の住持たちが寺内宗旨判形帖に判形を据えることを許しました。これにより、この年の冬、藩に提出された寺内宗旨判形帖には十二坊の住持たちの判形が据えられました。十二坊とともに浄専寺の住持も判形を据えることができました。
同年冬、寺内宗旨判形帖、もとのことく十二坊連判せり(『知新集』)
以前のように十二坊の住持と仏護寺の住持の二人が判形を据えるようになったのです。判形のことはこれで解決しました。しかし、興正寺が要望したのは、十二坊は仏護寺の塔頭ではないのであるから、判形を据えることを許してほしいということです。十二坊を塔頭として扱うのをやめるように求めているのです。これに対しては、藩は十二坊をそのまま塔頭として扱っており、藩の対応に変更はありませんでした。
興正寺以上に、強く仏護寺の塔頭ではないと思っていたのは、当の十二坊の住持たちです。十二坊の住持たちにとって、藩が十二坊を塔頭として扱うことをやめないことは腹立たしいものでした。そして、さらに十二坊の住持たちの怒りをかったのは仏護寺の住持の振る舞いです。仏護寺の住持は藩が十二坊を塔頭として扱っていることから、自身も十二坊を塔頭として扱うようになったのです。このため、仏護寺と十二坊は激しく対立します。
藩は十二坊を仏護寺の境内にある塔頭だとします。境内にある塔頭であるなら、それは真宗でいう寺中や侍僧と同様のものということになります。寺中や侍僧は本坊に仕える従属的な存在です。仏護寺の住持は、藩が塔頭だとしたことから、十二坊を寺中や侍僧と同様に仏護寺に従属するものとして扱うようになったのです。十二坊の住持たちが反発するのは当然です。事情を知る十二坊の檀家の人びとは、十二坊に味方し、ともに仏護寺に対抗しましたが、仏護寺の住持の振る舞いは藩の正式な見解をもとになされているものであるだけに、簡単にやめさせることはできませんでした。
仏護寺と十二坊の対立はその後も続きますが、翌元禄十六年(一七〇三)の八月、仏護寺の住持は藩に対し、自分は寺を出るので、寺を藩に献上するということを申し出ます。十二坊やその檀家の者たちが自分を悪者にして、人びとの帰依が薄くなったので、このままでは寺を維持することはできないというのです。
末寺並諸旦那迄も拙僧へ含意趣居申候、其後志違、寺相続も難成事ニ御座候、且又明教寺儀も其節任御指図、十二坊へ異見仕候処ニ不致承引、却而明教寺不通ニ罷成、無面目仕合ニ御座候、依之両寺ともに寺差上申候(『知新集』)
仏護寺と明教寺が連名で藩に提出した断書です。八月二十二日付になっています。仏護寺だけでなく、明教寺も寺を出るというのです。明教寺は、藩が寺内宗旨判形帖に塔頭の住持は判形を据えずに本坊の住持だけが判形を据えるように命じた際、それに逆らった十二坊の住持たちの説得にあたった寺です。その明教寺も、藩の指図によって十二坊の住持たち説得にあたったのに、十二坊の住持たちは従わず、逆に面目を失ってしまったため寺を出るというのです。
寺を出るといっても、この二つの寺の住持は本心から寺を出ようと思っているわけではありません。これは十二坊のせいで自分たちは寺を出なければならないほどの迷惑を蒙っているのだ、ということを藩に対して述べるために提出されているのです。それを理由に、藩に十二坊を罰してもらおうとしているのです。
この断書の提出をうけ、藩は、明星院、正清院という二箇寺の住持に命じて、状況を調べさせました。明星院は真言宗、正清院は浄土宗の寺院です。二人が仏護寺の住持に話を聞くと、仏護寺の住持は、十二坊の住持らは、十二坊が仏護寺の境内地にあるとはいわずに、いずれもそれぞれが所有する寺地にあるのだといっており、ひどい心得違いをしていると答えました。さらに仏護寺側は二人に、古老たちは十二坊はかつて仏護寺の御堂に詰め、勤行をしたという話を伝えているといったことも述べました。二人は、今度は十二坊の側の話を聞きましたが、十二坊側は。十二坊は仏護寺の寺内僧ではないし、古老の伝えなどはまったくないことで、それはでたらめな話だと答えました。
ことハ奢り、失礼の答多し(『知新集』)
二人には、十二坊の住持たちは言葉遣いが偉そうで、失礼な答えが多いと感じられました。
(熊野恒陽 記)