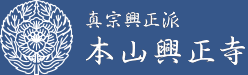【二百八十七】仏護寺十二坊 その九 仏護寺を優遇する藩
2025.11.26
仏護寺と明教寺の住持は元禄十六年(一七〇三)八月二十二日、連名でそれぞれの寺を広島藩に献上するという断書を提出します。十二坊と十二坊の檀家の者たちが、自分たちを悪者にするので、人びとの帰依も薄くなり、寺を維持することができないというのです。仏護寺と明教寺の住持は、藩にこのように申し出ることで、十二坊の住持たちを罰してもらおうとしたのです。仏護寺の住持は藩が十二坊を仏護寺の塔頭だとしたことから、自らも十二坊を塔頭と扱うようになりました。十二坊はそれに反発し、仏護寺と対立しました。仏護寺の住持は対立する十二坊の住持たちを罰してもらいたかったのです。
断書が提出されたことから、藩は事情を調べました。その結果として、藩は十二坊の側に争いの原因があると判断するに至りました。十二坊が塔頭であることは明白であるのだから、十二坊の側に非があるというのです。
仏護寺境内の事ハ、前々より絵図水帖あり、其外格式仏護寺境内の十二坊なるうへハ、今更吟味すへきことわりなし(『知新集』)
藩の意見です。十二坊のある地が仏護寺の境内であることは古い絵図や水帖でも境内ということになっているし、いろいろな行事の仕来りにおいても十二坊は仏護寺の境内に住む僧として扱われていることからも明らかなことなので、境内にあるのかないのかといったことはいまさら調べる必要はない、とあります。ここに出てくる水帖というのは検地帳のことです。検地帳は、簡単にいえば、土地の台帳です。検地帳は御図帳ともいわれます。その御図の当て字として水と書かれているのです。当て字とはいえ、検地帳は御図帳と書かれるより、水帖と書かれる方がはるかに多いです。
十二坊の住持たちはかねてから自分たちの寺は自分たちの寺地にあるのだといっており、仏護寺が断書を提出した際の藩の調べにも、自分たちは仏護寺の寺内僧ではないと答えていました。それにもかかわらず、十二坊を塔頭だとする藩の捉え方が変わることはありませんでした。藩は一貫して十二坊は仏護寺の境内にあるのだといい続けます。そして、そこから、十二坊は、自分たちの寺はそれぞれの寺地にあるのだとの偽りを述べ、檀家の人びとにも誤ったことを説いているため、仏護寺への帰依が薄くなって、仏護寺は寺を維持することが困難になったのだと結論づけました。
藩は、元禄十六年十二月十四日、仏護寺に対し、十二坊やその門下の人びとには仏護寺を疎かににしないように申しつけるから、このまま寺にとどまるようにと書いた口上書を渡します。その口上書には十二坊は仏護寺の境内にあることは去年もいった通りなので、十二坊にもそう伝えるようにとも書かれていました。
仏護寺境内之儀者、去年も如被仰出候、先規之通ニ被思召候、尤、十二坊ともへも其趣被仰聞候(『知新集』)
去年もいったというのは、元禄十五年(一七〇二)九月四日、寺社奉行から仏護寺に渡された口上書に、十二坊の住持に寺内宗旨判形帖に判形を据えることを認めるが、十二坊が仏護寺の境内にあることはこれまで通りだと書かれていることを指しています。十二月十四日の口上書にはさらに、仏護寺は寺が衰退したということなので、米、二百俵を下すとも書かれていました。仏護寺は明らかに優遇されているのです。
寺を献上するというのは仏護寺と明教寺が連名で申し出たことです。藩は明教寺に対しても、寺にとどまるようにと申し渡しました。
藩は十二坊に対しても、藩の意見を伝えています。
近年、本坊への仕方よろしからす、今より後、本坊へ対し、非礼非儀これなきようにいたし・・・先規のことく仏護寺境内の十二坊なる事ハよくわきまへ、塔頭の礼式、厚くまもるへきよし仰出されつ(『知新集』)
藩は十二坊に、近年の十二坊の本坊である仏護寺に対する振る舞いはよいものとはいえないので、今後は仏護寺に対し、無礼な振る舞いや、いわれのない行ないをしないようし、十二坊は仏護寺の境内にある塔頭であるという以前からの決まり事をよく理解した上で、塔頭としての礼儀を守るようにと伝えたのです。これに対し、十二坊の住持たちは、仏護寺を疎かにしないということはその通りにするが、十二坊が仏護寺の境内にある塔頭であるということについては、到底、了承することができないと答えました。
(熊野恒陽 記)